与えられた期限は、1週間。たった、7日間だ。その限られた時間で、オレ
たちは今後どうするのか明確な答えを出さなくてはいけない。
だが、それはあくまで猶予を与えられただけのように思えた。
オレたちが。
現実に引き戻される、までの。
今のこの状態が、非現実的だとは思わない。思いたくはない。けれど、周囲
から見れば、2人で逃げて、逃れてその先にある何かなんて、きっと蜃気楼の
ようなモノに過ぎないんだろう。
それでも、今ここにいる三橋の温もりは幻なんかじゃなくて。
「・・・・・阿部君?」
なあ、三橋。
オレたちが望んだことは、そんな途方もなくデカいものなんかじゃないよな。
珍しくオレより先に目が覚めて、オレを覗き込んでいた三橋の腕を軽く引い
て、落ちて来た身体を抱き締める。
オレの望みは。
そして。
こいつの、望みは。
あれから、数日が過ぎた。過ぎてしまった、と言うべきなんだろうか。
これからについて2人で話し合おうと試みたものの、三橋は「オレは阿部君と
一緒なら、それでいい」としか言わない。お前はどうしたいのかと聞いても、
返ってくるのは同じ答えだ。
それって結局オレ任せなだけじゃないかと思うのに、だけどそれが三橋の
意思であり気持ち全てなのだとしたら、文句の言い様がない。
とはいえ、ある意味追い詰められている今の状態で、全部オレに丸投げかよ
と思ったら、どうしようもなく苛立ってしまって、いつもなら三橋と一緒に
買い出しに出掛けるところを、オレひとりで行くとさっさと出て来てしまった。
ドアを閉める間際に垣間見えた三橋の表情が、頭から離れない。そんな寂し
そうな顔をさせたかったわけじゃない。あんな態度をとってしまった自分に
溜息をつきながら、重い足取りで最寄りのスーパーに行く。簡単に調理出来る
食材と、魚の煮付けなんかをカゴに入れ、レジに向かう手前の乳製品売り場で
パック入りの牛乳と、そしてプリンを3個手にとった。
罪滅ぼしだとか御機嫌取りだとか、そんなつもりはない。ただ、あいつの
笑う顔が見たかった。
買い物を済ませ、半時間ほどでマンションに戻る。まだ慣れない暗証番号や
カードキー操作にやや手間取りながら、そういえば三橋が部屋に残っているの
だからあいつにロックを開けてもらえば良かったのだと、エレベーターを降り
てから気付く。
まあいいかと苦笑しつつ、さっきのやり取りのことで少しばかりの気まずさ
を残していたのもあって、ドアを開けて小さくただいまと声を掛けたが、返事
はない。トイレにでも入っているのか、それとももしかして拗ねているんだ
ろうか。そっと三橋がいるはずのリビングに足を踏み入れたが、そこに三橋の
姿はなく。
三橋が、いない。
スッと血の気が引いたような感覚に、手にしていたビニール袋を床に落とし
てしまう。
「あ、べく、ん?」
三橋、と。大声で叫びそうになる直前に、やや離れたところから三橋の声が
聞こえた。
「ど、どした、の?」
ひょこりと三橋が姿を見せたのは、リビングから続くベランダのガラス戸の
向こうからだった。半分カーテンが閉まっていたのが死角になっていて、そこ
にいたのが見えなかっただけなのだと気付く。
「・・・・・何でも、ない」
「そ、そう? ・・・・・あ、プリン、だ!」
床に落ちたビニール袋の中から溢れたプリンの容器を、三橋は目敏く見付け
て瞳を輝かせる。
「さ、3個ある、よ?」
散らばったものを拾い集めながら、小首を傾げて問い掛けてくるのに。
「・・・・・オレは1個しか食わねェから」
「・・・・・お、オレ、2個・・・!」
「おう、ちゃんと食っちまってくれよ」
「うん!」
両手にプリンを掲げてガキみたいに喜ぶ三橋に、オレの心のささくれ立った
ものが、削り取られていく。こいつの喜ぶ顔を、ずっと見ていたい。
こいつを。
オレが、こんな風にずっと笑顔にさせてやりたい。
「・・・風、冷たくなってきたから閉めるぞ」
キスしてェな、なんて。三橋の顔を見ていたら、そのまま襲っちまいそうで
そんな衝動を誤魔化すように、開け放たれた窓に足を向ける。
そういえば。三橋は、ここで何をしていたんだろう。そんなことをぼんやり
思いながら窓枠に手を掛けて、ふと視線を泳がせたその先。
「っ、・・・・・」
河原に広がる、草野球のグラウンド。
練習の合間、互いに掛け合う声。
振り切ったバッドが、球を打ち上げる音。
置き忘れて来たかのような光景が、そこにあった。
「・・・・・は、し・・・」
「プ、プリン、とか、冷蔵庫に入れた、よー」
「三橋!」
続きのキッチンから小走りに戻って来た三橋が、不意打ちのようなオレの
大声に、あからさまに身体をビクリと震わせる。
「え、あ・・・阿部君・・・?」
怒ってる? 何で? オレ、何かした?
そんな表情の三橋にズカズカと歩み寄り、腕を強く引く。こんな時でも、
それはちゃんと右腕を避けているのに、苦い笑いが込み上げてくる。
「来いよ」
半ば引き摺るようにして、三橋をバスルームに連れ込む。ユニットではない
造りのそこは、部屋の大きさから考えてもこだわりがあるとしか思えないほど
洗い場も浴槽も広く、それこそ男2人が一緒に入ってもそう窮屈には感じさせ
ないゆとりがあった。
「ま、待って、あ、べく、・・・っ・・・・・」
僅かばかりの抵抗は、オレが三橋の身体をきつく抱き締めた途端、ピタリと
止んだ。おずおずと、オレの背に回された手。
「・・・・・三橋」
それが同意、と。シャツを脱がせる時間すら惜しくて、ぶつけるように唇を
重ねながら、腕の中の身体を弄る。少しずつ露になっていく素肌を撫で上げ、
手の平だけじゃなく唇や舌で、その感触を確かめるみたいに丹念に味わう。
「ん、ん・・・っ、あ・・・」
零れる吐息も嬌声も。
肌も体温も匂いも味も。
全部。
少なくとも今は、オレだけのものだ。
「あ、べく・・・の・・・・・」
半ば無意識に下肢を擦り付けてしまえば、それに気付いた三橋が熱っぽく
潤んだ瞳が、ねだるように見つめてくる。
「欲しい?」
「ほ、しい・・・」
素直に返された答えに口元を弛ませ、三橋の指がぎごちなくファスナーを
下ろし、下着の中に潜り込んでいくのを見下ろす。
「い、い・・・?」
足元にしゃがみ込んで、上目遣いに問うてくるのに頷けば、ふにゃりと笑う
子供っぽい表情と、その手にしたオレの張り詰めた性器とが酷くアンバランス
で、そんな光景にさえもどうしようもなく煽られる。
「ま、またおっきくなった・・・」
捧げ持った赤黒いそれを手の平で包み込み、ゆるゆると扱き上げながら、
三橋は何の躊躇いもなくその先端に舌先を這わせ、裏筋に添わせるようにして
亀頭を口に含んでいく。仕草自体は何度かさせた行為故か、それなりに慣れた
ように見えるが、愛撫そのものはまだぎごちない。確実にイイところを狙い
すましたように突つかれるより、微妙に外しては時々クる箇所を掠めるのが
ジワジワとキて、オレは好きだ。
それをしているのが、こいつだからというのが多分ホントの理由なんだろう
けれど。
「すげーキモチイイよ、三橋」
欲に掠れた声で囁きながら髪を梳くように頭を撫でると、オレのを口一杯に
頬張りながら、見上げてくる瞳が嬉しそうに細められる。誉められて気を良く
したのか、口淫がリズミカルに速度を増していく。限界ギリギリまで昂った
それが、時折喉の奥を突いてしまうからか苦しげな表情を垣間見せながらも、
健気に舌を使い先走りをチュウチュウ吸い上げてくるのに合わせて、オレも
ゆるやかに腰を動かす。
「・・・飲んで」
告げれば、合わせた目をパチッと瞬かせて、一際強く口を窄めるのに。
「く、っ・・・・・」
「んん、・・・っ、・・・・・ふ、・・・」
上顎を擦り上げるようにして押し込んだ先端が爆ぜ、ドクリと白濁が三橋の
口の中に注ぎ込まれる。喉に絡むらしいそれを飲み下し、鈴口も綺麗に舐め
取った三橋の唇から少しだけ溢れ出た雫を指先で掬い、目の前に差し出す。
「オ、レの・・・、阿部君の・・・全部、クダ・・・サイ」
半ば恍惚とした貌でオレの指先もペロペロと舐め清めた三橋の、ほんのり
紅潮した頬を撫で、するりと耳朶をくすぐりながら、屈んでその耳元に問い
掛ける。
「お前も気持ち良くしてやるよ・・・どこがイイ? 同じようにしてやろうか
・・・それとも・・・・・」
くすぐったがりの三橋は、耳元にかかるオレの吐息にいちいちピクリと身体
を震わせ、また服を着たままのオレの袖口にしがみつく。
「・・・ほ、う・・・が・・・」
「ちゃんと言ってみ」
いっぱいしてやるから、と。軽く耳を噛めば、崩れるようにして三橋が腕の
中に収まってくる。
「り、両方・・・っ」
「両方じゃ、分かんねェだろ」
我ながら意地の悪い、とは思う。けれど、やはり三橋の口で、三橋の口から
その言葉を聞きたい。
「っ、・・・お、ち・・・ちん、と・・・お、おし、り・・・っ・・・両方、
してほし、い・・・いっぱ、い・・・」
「・・・・・いっぱい、ね」
羞恥に目元を赤く染めながら告げられたそれに満足して、オレは三橋の望む
ままに。オレの望みのままに、その身体にむしゃぶりついた。
結局、晩飯どころかプリンも食わせてやれなかったなと申し訳なく思いなが
ら、すっかり意識を飛ばした三橋の身体を綺麗に洗い、柔らかなバスタオルに
包み、丁寧に拭いて、パジャマを着せてやる。ベッドに運ぶまでに目を覚まし
たら、すぐに晩飯の支度をしてやるつもりだったのだが、結局そのまま寝入っ
てしまったようで、布団を掛けて小さくおやすみと囁いた。
数日前に、性急にだったとはいえ身体を繋げたばかりだというのに、まるで
もうずっと長いこと三橋に触れていなかったかのように、浅ましくガッついて
しまったのを少しばかり反省しつつ、でもそれは三橋も同じだったのか、互い
に貪るように求め合い与え合った。気を失う寸前、三橋が掠れた声でもっとと
ねだってきた時には、さすがにオレももう息切れ寸前で。
それでも。
もっと、もっとと欲する気持ちは、疲労した身体とは裏腹に収まることは
なく。
一体。
本当に。
どれだけ貪欲なんだろう、オレは。
オレたち、は。
互いに満たし、満たされながら、それでもまだ足りないというように。
燻っていたものに火をつけたのは、三橋が見ていたあの光景だった。
三橋は、どんな思いであれを眺めていたのだろう。
それを考えると、何かに突き動かされるように三橋を抱いていた。
「・・・・・オレは・・・」
大きく息を吐き出しつつ、三橋の眠るベッドから立ち上がると、部屋の角に
ぽつんと置かれたバッグに手を伸ばす。勝手に中を探ることを心の中で謝り
つつ、開けっ放しのそれをそっと覗き込む。
前に見たように、そこには本当に着替えしか入ってはいない。中に手を突っ
込んでみても、あるのは布の感触ばかりだ。
「・・・・・ああ・・・」
やはり。
ある、だろうと。
きっと。
三橋なら、手放さずに持って来ているだろうと。
何の疑いもなく、そう思っていたものは、そこにはなかった。
「・・・三橋・・・・・」
なあ、三橋。
オレは。
オレたちは。
どこかで何かを間違えてしまったんだろうか。

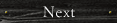 (coming soon)
(coming soon)